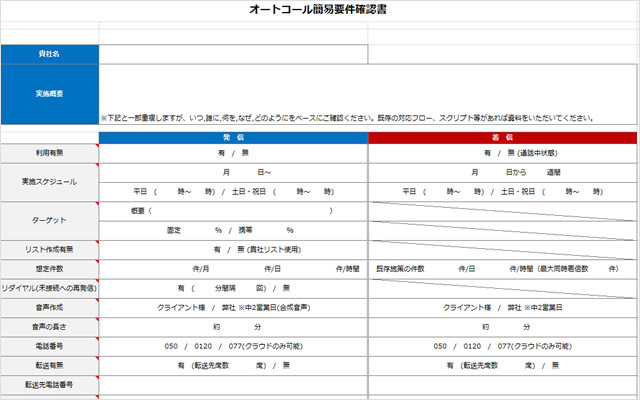オートコール V.S. オペレーター どちらを使うべき?

電話の受発信業務といえば、オペレーターやアポインターの仕事だと一般的には考えられています。
しかし、コールセンター業務はストレスの多い仕事のため、慢性的な人材不足に悩まされている企業様も少なくないでしょう。さらには、人件費の高さも避けられない悩みです。
そこで検討できるのが「オートコールサービス」の導入です。本記事では、オペレーターと比較しながらオートコールのメリット・デメリットをご紹介します。
オートコールとオペレーターの比較
オートコールとオペレーターを「反応率」「コスト」「手間(必要な作業)」の各項目で比較した表が下です。
| オペレーター | オートコール | |
| 反応率 | 2~3%程度 | 2~3%程度 |
| コスト | 人件費+通話料 | 発信費 1通話当たり5~20円程度(※導入形態により異なる) |
| 手間(必要な作業) | オペレーターの採用・教育・勤務管理など | 発信依頼・打ち合わせなど |
反応率は、どちらも2~3%程度と変わりません。
一方、コスト面では、オートコールが有利です。オートコールの導入形態がシステム導入型の場合は初期費用が高額になりやすいですが、クラウド型、委託型の場合は初期費用が掛からないケースが多く、発信費も1通話当たり約5~20円と手頃です。オペレーターを使う場合、募集から採用、教育と初期コストがかかるうえ、高時給のため人件費もかさみがちです。
また、オペレーターの場合、シフト管理や給与の支払いなど、雇用に関わるさまざまな業務が発生します。その割に離職率が高く、かけたコストが回収できないケースも多々あります。オートコールの場合は、そもそも人材採用の必要がないため、こういった手間は発生しません。
オペレーターのメリット・デメリット
では、まずオペレーターのメリット・デメリットから見ていきましょう。
オペレーターのメリット
オペレーターのメリットは、人間が直接対応してくれるため、双方向性のコミュニケーションが取れる点です。わからないことはその場で質疑応答して解決できるため、オペレーターの対応さえ良ければ顧客満足度アップにつながるでしょう。
オペレーターのデメリット
先ほどもお伝えしたように、オペレーターの採用・教育にコストがかかる割に離職率が高いという点が一番のネックになります。 繁忙期などで大量にコールしたい場合などは、人員確保も困難になります。
また、人対人のコミュニケーションのため、本来の目的(アポ獲得・リサーチなど)以外の無駄な会話が発生してしまい効率的ではありません。さんざん会話した後で、結局、アポが取れなかったり調査に協力してもらえなかったりすれば、通話料とオペレーターの時給はコストがかさみ、コールセンターの費用対効果が低くなってしまいます。
電話を受けるお客様の心理的なハードルが高いこともデメリットです。営業を断るための口実を考えるストレスを与えてしまい、会社や商品に対する印象が低下してしまう可能性もあるでしょう。
オートコールのメリット・デメリット
これに対し、オートコールのメリット・デメリットは以下のようになります。
オートコールのメリット
オートコールの一番のメリットは、1通話当たり5~20円程度と格安で低コストな点です。しかも、反応率は2~3%とコストパフォーマンスは高いのです。
また、システムを使って発信するため、短期間で一斉に大量のコールが可能です。
さらに、あらかじめ録音した音声を再生してメッセージを伝えるため、受け手のコミュニケーション・ストレスが少ない点もメリットです。
オートコールのデメリット
一方、オートコールのデメリットとして、固定電話にしかかけられないサービスがほとんどであることが挙げられます。
このため、
- 固定電話を契約していない層にはリーチできない
- 若年層をターゲットにしづらい
という点がデメリットです。
また、あらかじめ録音された音声を一斉発信するサービスのため、
- 録音音声が苦手な層には受け入れられない
といった面もあります。
オートコールのメリット・デメリットについて、詳しくはこちらの記事もご覧ください。
導入すべき?オートコールのメリット・デメリット
オートコール+オペレーターの活用術
オペレーターにもオートコールにも、それぞれメリット・デメリットがあります。ここで、どちらか一方のみを運用するのではなく、欠点を補完するような活用を考えてみましょう。
テレアポの補完(リストの精査・アポイントの確認)
アポインターや営業マンがテレアポを行う前に、テレアポの効率を上げるための下準備として、最低限、不通の番号は排除しておきたいものです。オートコールを使えば、指定した番号に一斉にコールし、発信結果をデータベース化したものを納品してもらえます。
また、プッシュボタン選択による簡単なアンケート調査が行えるので、その回答結果により興味関心の高い見込み顧客から重点的にテレアポすれば、アポ率・受注率の向上が見込めます。
オペレーターが受け切れない「あふれ呼」をオートコールで受ける
受電コールセンターでは、お客様からの受電が集中すると、回線がパンクしてつながらなくなるケースがあります。これが「あふれ呼」とよばれるものです。電話をかけているお客様側には話し中として認識されるため、待たされてしまったり繋がらなかったりする分だけ顧客満足度の低下につながってしまいます。受電内容が申し込みなどであれば、機会損失にもなります。
これを避けるためには、あふれ呼をオートコールへ外線転送することが効果的です。そうすることで、お客様からしても相手側が話し中ではなくなり、コールセンター側は回線に余裕ができた時点で重要な受電については即時、折り返し対応を行うことができます。このように、オートコールを受電コールセンターで活用することで顧客満足度の向上につなげられます。
まとめ
オペレーターにもオートコールにもそれぞれ、メリット・デメリットがあります。オペレーターの双方向のコミュニケーションができる点も、オートコールの低コストであるメリットも享受するためには、オペレーターを必要最低限だけ確保し、代替できる部分をオートコールで運用するベストミックスを探るのが賢い選択かもしれません。
オートコールサービスに関して「こんなことはできるだろうか?」と疑問が沸いたら、クラウド型でコストパフォーマンスの良いメガコールを提供する当社に、ぜひご連絡ください。
オートコールの具体的な活用事例については、こちらの記事でも紹介しています。
オートコールとは
オートコールのメリット・デメリットをもっと知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
オートコールとは
オートコール活用のご相談やお問い合わせは下記ボタンより